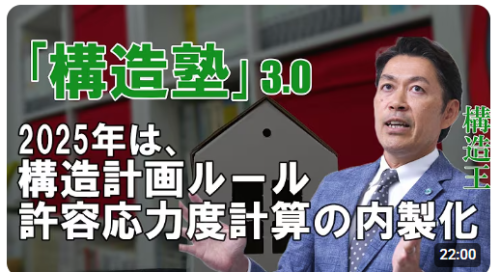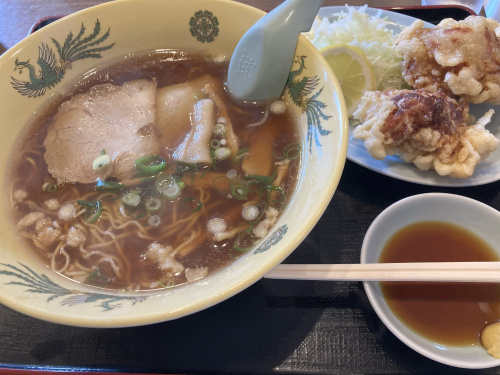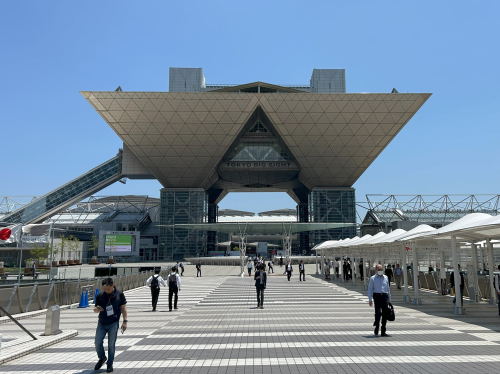スタッフブログ
2025.02.08
パッシブハウス建築の経緯
おはようございます!
最近は朝4時台に起きてゴソゴソしている中桐です。
さて、現在新しい挑戦として、パッシブハウスを建築中なのですがそこに至った経緯を少しお話しておきたいと思います。
まずパッシブハウスって何??という方もいらっしゃると思うのでその辺りを90秒で簡単に。
↓YOUTUBE動画です。※注意 音が出ます。
という感じで性能のその先を考えた家づくりです。
もともとHEAT20 G2(断熱等性能等級6)クラスの家づくりをしていた私達としては、G3が出てきた当初、省エネ地域区分でいうと、6地域の岡山倉敷ではコスパの観点からもここまでは必要ないかなと思い、基本的にG2~G2.5の家づくりを続けていました。(※省エネ地域区分についてはこちら YKKapサイト)
そんな中で、1年ちょっと前に愛媛のアーキテクト工房Pureさんとの出会いがあり、そこで初めてパッシブハウスを体験しました。(代表の高岡さんはパッシブハウスジャパンの理事でもあり、愛媛にも何度もお伺いさせて頂き技術的な話も含めとてもお世話になっています。)
ただ、その時は快適だったのは間違いないのですが、11月で外気温がそれほど低いわけでもなかったので、体感的な差は感じにくい状況でした。(#その時は温熱的なことより、施工技術の高さに驚愕した記憶が強い)
その後、その経験を踏まえ全国のパッシブハウスを様々な季節に何棟か体験できる機会があり、体感を重ねることでじわじわと確信を得たことがあります。すべてにおいて共通だったこと。
それは、明らかに自分を纏う空気が違うということです。
自然素材を使われているところが多いのでそういう意味での空気感はもちろん違うのですが、それ以上に温度ムラというか全身に触れる空気の温度差(頭から足の先まで)が無い、若しくは極端に少ないということです。それが年中どこにいても一定であるということ。暑い寒いはあくまでも外の話しであって家の中は常に一定です。
建築地が日本のどこであろうと、もっと言うと世界中どこに建てようと一定です。
これがいわゆる本質を理解せず数字追いになっている最近のG2・G3のすまいとの圧倒的な差を生んでいます。
(#ちなみに私もHEAT20正会員ですが、HEAT20の提唱するG1~G3は単なるUa値競争ではありません。)
この住まいの良質な環境がもたらす恩恵は健康面はもちろん、暮らしの質の向上という観点からも住まう方に非常に有益であると考えています。そしてさらに、未来へ向けて環境にも良いとなれば選択の余地はないのではないかと私は思います。
そう感じてからは、機会があればパッシブハウスに挑戦しようという意識になっていました。
世界基準で考える日本の家のレベルの低さも痛感し、よりよくしていきたという思いもあり…。
(#このあたりは話せば長いので、また別の機会に(笑))
そんな思いの中、予定していた新築のお客様の着工が諸事情で半年ほど延期になり、ちょうど前モデルハウスもお引渡しし、お客様に見て頂くモデルハウスが無い状態でしたので、この間に1棟建てようということに。
当初は、このご時世なので付加断熱をせずにギリギリいけるG2.5ぐらいの性能の家をどれだけコストを抑えて建てられるかというコンセプトでのモデルの予定でしたが、このタイミングでのこのチャンスはある意味、行け!ということだなと直感でパッシブハウスに挑戦することを決めました。
それを決めたのが昨年の6月で、その6月中にプランをまとめ7月頭に確認申請と長期優良の申請を提出し、8月のお盆明けから着工というなかなかタイトなスケジュールで進めました。
そして、9月に上棟し今に至る、といった感じです。モデルなので途中抜けたりもしていますし、全てを決め切ってない所も多々あったので、時間はかかっていますが、やりながら考えながらチームで相談しながら進めています。
おそらく5月ぐらいには公開できるのではないかと思っていますので完成の際にはぜひご覧ください!
その時に、ここでは書ききれない思いやこだわりの点、構造を含めたより建築的なこと、もちろんどういった暮らしが出来るかや、そもそもの建築コスト、光熱費のこと、総合的な反省点等、現地で体感して頂きながらゆっくりとお話できればと思います。
では、寒い日が続きますのでご自愛ください。
素敵な1日を!


現在外装材施工中です!