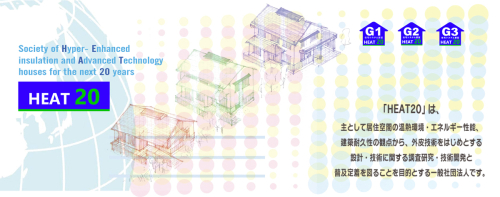スタッフブログ
2025.09.04
HEAT20の新しいものさし「G-A」「G-B」とは?
おはようございます!
秋の花粉症というか鼻炎が始まりだした中桐です。もれなく年に2回訪れます…涙
さて、話は変わりますが今日は新しい基準のお話です。みなさんHEAT20ってご存じですか。
このHEAT20は多くの学識経験者、住宅供給者、建材等の供給者等によって活動している民間の団体です。
私も所属していて、各種のワーキングにも出来る限り参加しているのですが、家づくりを少し勉強されている方ならすぐに出てくる断熱性能を示すワード。「G1」「G2」「G3」という言葉。これを定義したのがHEAT20です。
国の断熱等性能等級5、6、7はこれを参考に決められたと思われます。(正式に発表されていないのですがおそらく)
今日はそのHEAT20がこの度、新しく定義した「G-A」「G-B」について、私なりに少し解説したいと思います。
※ちなみに今年7月にHEAT20から出たプレスリリースはこちら。
では、さっそく。まず簡単に言うと、
冬に加えて、夏と中間期の基準ができた!
G1〜G3 → 冬のあたたかさを測るものさし
G-A・G-B → 夏と中間期の快適性を測るものさし
「G1」「G2」「G3」っていうのは【冬にどれだけ暖かく過ごせるか】を示す目安。
そしてこの度、新しくできた「G-A」「G-B」という基準は【夏や中間期にどれだけ快適に、そして省エネで過ごせるか】を示す目安。そう考えてもらって大丈夫かと思います。
つまり、家の性能を「冬だけでなく、夏と中間期も含めて一年通して考えられる」ようになったということです。
なんで夏の基準が必要?
みなさん感じているように、夏と冬のバランスが温暖化(気候変動)で変わってきています。今後はこれが常態化していく可能性が極めて高い。よって、
猛暑日が増えて、冷房なしでは暮らせない日が多くなる
断熱性能が高いほど、しっかり日射を遮らないと室温が上がりやすい
冷房をガンガン使えば快適だけど、光熱費が跳ね上がる
このようなことになってきます。そんな課題を建築的に解決するのが「G-A」「G-B」です。
G-AとG-Bってなにが違うの?
G-B(よりしっかり夏に強い家)
平成28年省エネ基準適合住宅に比べて冷房負荷を約40%カット。少ないエネルギーで家全体を冷やせるイメージ。
ただし地域によってはハードルが高い場合も。G-A(現実的に取り入れやすい基準)
平成28年省エネ基準適合住宅に比べて冷房負荷を約30%カット。無理なく取り組めて、夏も快適。
ちなみに北海道や東北の寒冷地では、G-Aでも十分に全館冷房に対応できるレベルとされています。
ポイントは「室温」じゃなく「エネルギー」
冬の基準(G1〜G3)は「最低室温〇℃」(※諸条件あり)という指標がありました。
でも夏のG-A・G-Bでは「冷房に必要なエネルギー」で比べます。
理由はシンプル。
最近の高性能住宅は部屋ごとに冷やすより、シンプルな冷房で家全体を快適にすることが多くなったから。
だから「どれだけ効率よく涼しくできるか」で見る方が分かりやすい。
冬と夏をセットで表せる
この基準ができたことにより、冬と夏の基準を組み合わせられること。
冬がG2、夏がG-B → G2-B
冬がG3、夏がG-A → G3-A
これなら「この家は一年中快適で省エネ」とひと目で伝わりますが、この「G-A」「G-B」は「G1」~「G3」のように一定に認知を得るまでには、少し時間がかかりそうな気がしています。(あくまで個人的な見解です…笑)
もうお分かりだと思いますが、この基準で最高位はG3-Bだと言えますね。
パッシブハウスとの違いも少しだけ
ちなみに、この度完成した弊社の新モデルハウスはパッシブハウス認定予定です。
このパッシブハウスとの違いはというと、HEAT20は、日本の気候や暮らし方に合わせて研究者が提案している基準。
「どのくらい快適か、省エネか」をイメージしやすくしてくれる言わば『日本版のものさし』です。
一方で、パッシブハウスはドイツ発祥の世界基準。数値を厳密に計算して、国際的に認められる「認定」が受けられる仕組みです。
例えるなら…
HEAT20は「日本国内に特化した通行手形」
パッシブハウスは「世界に通用するパスポート」
どちらが上とか下とか、そういうカテゴリーではなく、どちらも「いい家をつくるための道しるべ」。
目的に応じて両方を理解しておくと、より安心して家づくりに取り組めると私は思います。
まとめ
HEAT20の「G-A」「G-B」は、夏の快適さと省エネを考える新しい基準
冬のG1〜G3と組み合わせることで、一年を通した住宅性能を表現できる
パッシブハウスとの違いは「国内向けの目安」か「国際的な認定」かという立ち位置
これからの家づくりは、冬だけでなく夏の快適さもあわせて考えることが大切です。
以上、今日は家づくりの基準の話でした。
写真もなく読み物的なブログになりましたが私なりに、かみ砕いたつもりですので参考になれば幸いです。
では、素敵な一日を!